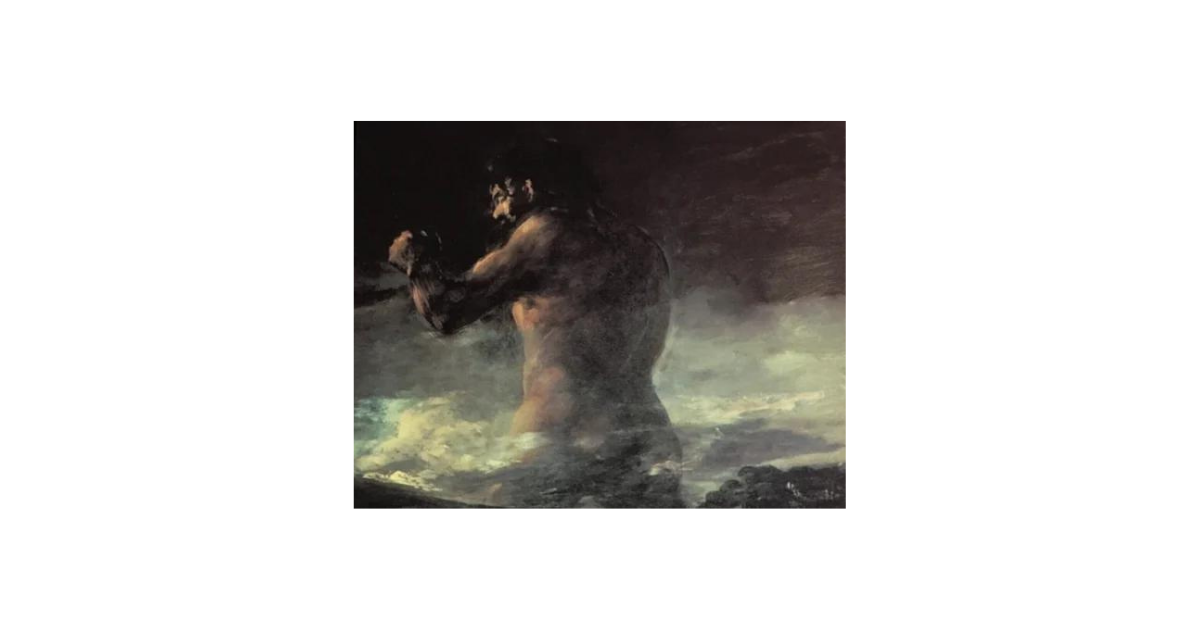
三角座りをして背中を丸め、抱えた膝に顔を埋めたまま、巨人はもう20年くらい動こうとしない。最後に巨人が動いたのを見たのは僕がまだ10代の頃、長かった夏が終わって半袖から忍び込む空気の冷たさにふと驚かされるような夕方だった。僕は実家のマンションの屋上に佇んで、そこから一望できる地方都市の家々を見ていた。あの頃、何かを相対化したくなった時に、僕はいつもそうしていたのだ。
それは一瞬の動きだった。こっちはいい天気なのに遠くの空は暗い雲に埋め尽くされていて、山沿いの雲間に稲妻がまさに「稲妻」という形で光った。それに目を奪われている間に既に巨人は立ち上がっていた。立つと手前に建つ市営住宅より高く見え、おそらく4、50メートルくらいだろうか。巨人は振り返って稲妻が光った辺りを指差した。そしてここからは実は記憶が曖昧というか、後付けのような気もしているのだが、巨人は僕と目を合わせたように思う。そして何かを言った(口を動かした)気がする。
また、こっちは間違いなく覚えているのだが、僕はそれに応えるように歌を歌ったのだ。
自分の意識に先行するほどに淀みなく言葉が溢れてきて歌となって口からこぼれ出していく。その当時よく聴いていた音楽に合わせて、一種の替え歌のようなものだったが、自分が今口にしていることと目にしているもの、そして心に浮かんでいるものが完全に一致する、それまでに味わったことのない快感があった。曲を変え止まらずに30分くらいは歌っていたんじゃないだろうか。
きっと巨人が僕に歌わせたのだ。巨人を讃える歌だったんじゃないかと思う。
その歌はもう、欠片も思い出せないけど。
それから巨人は動かなくなった。僕はその日、暗くなるまでずっと彼を見つめ続けた。
次の日も、また次の日も、僕は毎日のように屋上から巨人を眺めた。風邪をひいて学校を休んでいたのに寝床を抜け出して見にいったこともあった。
巨人は今と同じ姿勢で、動くことはなかったけど、見るたびに彼が動いたときの様子を思い出すことができた。
そのうち見にいく頻度は減っていったけど、就職のためこの都市を離れるまで、僕は断続的に巨人との逢瀬を繰り返した。
「なるほど。少年は奇跡を体感したわけだ」
巨人の背を登りながら夏海は笑った。
彼女はこの街に来るのが初めてだから、巨人のことをただの伝説くらいに感じているのだろう。僕だって昔を知らなければ、今足元にあるのが巨大なヒト型生物の一部だとは信じられないかもしれない。
巨人の首根っこの辺り、最も高い位置にたどり着く。とはいえビルの10階ほどの高さもないが、眺望は開けた場所だ。僕はそこから見える、何度改修してもデザインから古さが隠せない建物を指差した。
「あれがあなたの実家のマンションなんだ。けっこう遠く見えるけど」
「車なら10分もかからないよ」
「確かにいい景色だね。落ち着く。初めてのご両親との挨拶に緊張している私を気遣ってくれたことに感謝いたします」
冗談めかして堅苦しい口調でそう言った夏海は右手でお腹を愛おしそうにさすった。僕の両親はきっと彼女を一目で好きになるだろう。僕がそうだったように。
僕たちの未来に障害は今のところ見当たらない。
二人の足元で、巨人は静かに呼吸している。
20歳になった日の朝、部活の長期合宿から1月ぶりに家に帰った僕は、巨人の不在に気づいた。先輩の車で家の近くに落としてもらった時、そこから見えるはずの背中が見えなかった気がして、僕は家に戻る前に屋上にのぼって確かめたのだ。
そこにいるはずのものがいないのに、不思議と違和感のない景色が広がっていた。喪失感もなく、その時の僕は普通に不在を受け入れていたのを思い出す。そういう時期が来たのかな、という変に達観した感覚だったと思う。そして、当時できたばかりの彼女に電話した。
「巨人はいなかったよ」「あ、あの話? でしょう? それより久々にさ…」
嫌になるほどお互いを知るような学生らしい交際は半年ほどで終わり、ふと思い出して屋上にのぼったら、いつのまにか巨人は戻ってきていた。
いや、やっぱり巨人はずっといたのだと思う。
あの朝は、高速代を浮かすため深夜に下道を走って帰ってきた寝不足の目で見間違えたのだろう。
「めっちゃ似てるね」
夏海の意外な言葉に一瞬狼狽えてしまった。
「俺が父親と?」
見た目は母親似とずっと言われ続けてきた僕だが、帰りの新幹線で夏海はそう指摘した。
「見た目というか、喋り方」
そりゃあ長い時間をともに過ごした人間なんだからそうだろうけど、僕はなんだか恥ずかしくなってそれを誤魔化すように適当な軽口を叩く。
喋り方が似るということは考え方が似るということだろう。それは遺伝子の仕業ではなく後天的なものに違いない。人は結局誰かに似ていってしまうのだ。
僕は夏海の話し方が僕に似てちょっと育ちの悪い感じになり始めているのに気づいている。
誰にも似たくないと考える時期は僕にもあった。そういう時期は誰にでもあるんじゃないかと思う。
人に似ることで自分が自分でなくなっていくように感じてしまうという、若気の至りこの上ないアレだ。で、どうするかというと他人をシャットアウトするんだけど、そんなことをしても自分の空虚さを見つめることになるだけで、その上寂しくて仕方がない。
就活のストレスもあって、そんなシャットアウトモードに入っていた僕は、中高生の時のように毎日屋上にのぼっていた。今思えば虚しいし寂しい日々だったけど、悪くない時間だった。巨人は静かに座っていた。
夏海と知り合ったのは20代後半、いろんな失敗を経て「今度は上手くやろう」と慎重に関係を築こうとする年頃だった。
あまり性急に相手を知ろうとせず、自分を伝えようとせず、長い試合時間を見越して老獪なタイムマネジメントをするベテラン選手のように、要するにいろいろ小出しにする方法を選んだ。
それは上手くいったんだと思う。こうして結婚までたどり着いたわけだし、お互いに嫌いになるまで好きになるような愚は犯さなかった。今でも僕は夏海の知らない僕について話すし、夏海もそうする。僕らはゆっくりと似てゆくのだろう。それでいいのだと思う。
「今度行く時も、あの丘にはまたのぼりたいなぁ」
夏海は巨人のことを「丘」と言った。
僕は訂正する必要を感じなかった。僕にもあれが丘に見える日が来るんだろう。そう遠くない未来に。
僕は夏海のお腹に目をやった。この子も自分たちに似ていくんだろう。そしてそれを嫌がって、そのうち僕のように受け入れるんだろう。